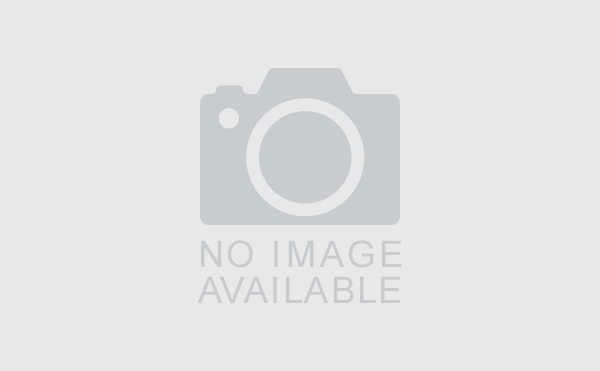【今日の豆知識】上棟式のもうひとつの主役「棟札(むなふだ)」とは?
上棟式では、ノサ(のさ紙)と並んで大切なものがもうひとつあります。
それが「棟札(むなふだ)」です。
棟札は、建物の一番高い位置──**棟木(むなぎ)**に取り付けられる木の札のこと。
そこには、この家の“記録”と“祈り”が刻まれています。
棟札とは?その役割と由来
棟札の歴史は古く、平安時代からすでに存在していたといわれます。
もともとは、神社や寺院の建築で「この建物を誰が、いつ建てたか」を神様に報告するためのものでした。
その名残が、現代の住宅にも受け継がれています。
棟札には、次のような内容が記されます
- 建物の名称(例:〇〇邸)
- 建築年月日
- 施主(家主)名
- 棟梁や施工者名
- 工務店・建築会社名
つまり棟札は、建物の誕生証明書のような存在なのです。
棟札に込められた祈り
棟札は単なる記録ではなく、**「この家が永く安全でありますように」**という祈願の証。
上棟式で神主さんがお祓いを行ったあと、
棟梁の手によって屋根裏の棟木にしっかりと取り付けられます。
普段は目にすることのない場所にある棟札ですが、
その奥には、家族の安全・繁栄への想いがしっかりと込められています。
棟札は“未来へのメッセージ”
棟札は、将来リフォームや建て替えをする際に再び姿を現すことがあります。
そこに書かれた日付や名前を見ると、
「この家を建てた人たちの想い」が時を超えて伝わってくる――
そんな不思議な温かさを感じます。
つまり棟札は、未来の誰かへのメッセージでもあるのです。