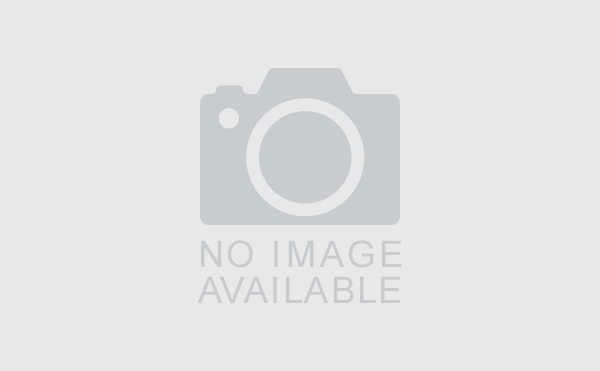上棟式に欠かせない「ノサ(熨斗)」とは?
家づくりの大きな節目「上棟式」。
この日に飾られる“ノサ(のさ)”を見たことがありますか?
棟木(むなぎ)の先端や高い場所に、紅白や金銀の紙を重ねて折った飾りが付いているのを見かけたことがある方も多いでしょう。
実はこの「ノサ」、昔から続く日本の建築文化の象徴なんです。
⸻
ノサとは?その意味と由来
ノサとは、上棟式で建物の無事と繁栄を祈るために棟木に取り付ける縁起物のこと。
漢字では「熨斗(のし)」や「御幣(ごへい)」とも書かれます。
もともとは、神様に感謝と祈りを捧げる神聖な供物の象徴で、
神前に捧げる布や紙の「しるし」として生まれました。
つまりノサは、
「この家を建てさせていただく感謝」
「末永く安全でありますように」
という願いを形にしたものです。
⸻
ノサの色と形にも意味がある
ノサには紅白や金銀など、いくつかの色があります。
それぞれに深い意味が込められています。
多くの場合、これらの色の紙を重ねて美しく折り、棟木に飾ります。
地域によって形や折り方が少しずつ異なり、地元の職人文化が色濃く残っている部分でもあります。
⸻
上棟式でノサを飾る理由
上棟式は、家の骨組みが完成したことを神様に報告し、
工事の安全と家の繁栄を祈願する大切な儀式です。
その中でノサは、**神様に向けて掲げる“感謝の印”**として飾られます。
棟の一番高い場所に取り付けられたノサが空に向かってひらめく姿は、
「家が誕生しました」という合図のようでもあり、どこか神秘的な美しさがあります。