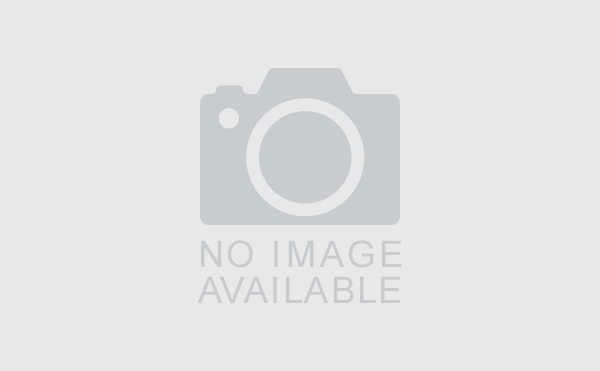住まいづくりに役立つ心理学
― 心地よさの“理由”をデザインする ―
家は、ただ「住む場所」ではなく、心を整える場所です。
朝、光が差し込むリビング。帰ってきたときにふっと安心できる玄関。そんな小さな“心の反応”こそ、住まいづくりの本質にあります。
実は、心地よさの裏には「心理学」が深く関わっています。今日は、Virestoが考える“心理を活かした家づくり”のポイントを少しご紹介します。
1. 光と心理の関係
人は自然光を浴びると、セロトニンという「幸せホルモン」が分泌されます。
明るい窓辺、朝日が入るキッチン――それだけで気持ちは前向きになります。
一方で、夜は照明を落とすことでリラックスできる「メラトニン」が働き、眠りの準備が整います。
**“光の設計”**は、暮らしのリズムを整える大切な心理デザインです。
2. 素材がもたらす安心感
木の温もり、畳の香り、漆喰のやわらかい表情。
人は自然素材に触れると、心拍が落ち着き、ストレスが軽減されると言われています。
Virestoの家づくりでは、「デザインの美しさ」だけでなく、触れた瞬間の感覚を大切にしています。
素材の選び方ひとつで、家の“優しさ”は変わるのです。
3. 色が左右する感情
色は、言葉よりも早く感情に働きかけます。
たとえば――
- 青:集中・落ち着き
- 緑:安心・癒し
- 黄色:元気・社交的
- 白:清潔・広がり
家全体を「どう感じてほしいか」を意識して、配色を決めることが、居心地の良さにつながります。
4. 動線と心の余裕
生活動線がスムーズな家は、ストレスを減らします。
「玄関→洗面→リビング」が自然につながると、帰宅後すぐに手洗いでき、家族が快適に過ごせます。
心理的に“ムダのない流れ”をつくることで、心にも余白が生まれるのです。
心をデザインするということ
心理学を意識した家づくりは、決して難しいものではありません。
「気持ちいい」「落ち着く」「また帰りたい」
その直感的な感覚の中に、すでに心理が息づいています。
Virestoは、そんな“感情をデザインする建築”**を目指しています。